【最新版】特定荷主の義務と省エネ法ガイドライン解説 | ナカノ商会 輸送サービス
2025.02.25

地球温暖化対策が叫ばれる中、物流業界でも省エネ化が急務となっています。
2013年の省エネ法改正で導入された「特定荷主」制度は、荷主にも省エネ化を推進する義務を課すものです。
本コラムでは、特定荷主制度の概要、義務、省エネ化を推進するためのガイドライン、よくある質問などを詳しく解説し、荷主の皆様の疑問や課題解決を支援します。
ぜひ、最後までお読みいただき、自社の物流における省エネ化推進にお役立てください。
特定荷主とは?
地球温暖化が深刻化する中、2024年現在、あらゆる業界で省エネルギー化への取り組みが急務となっています。物流業界も例外ではなく、省エネ法の改正により、荷主にも積極的な役割が求められています。
その中で注目されているのが「特定荷主」制度です。特定荷主とは、年間の貨物輸送量が多い荷主のことで、省エネ法に基づき、物流における省エネ化を推進する義務を負います。
具体的には、以下の条件を満たす荷主が特定荷主に該当します。
- 貨物輸送量が3,000万トンキロ以上
- トラック輸送で9万トン以上の貨物を取り扱う
これらの条件に該当する荷主は、省エネ法で定められた義務を果たす必要があります。
では、なぜ特定荷主制度が導入されたのでしょうか?
背景には、物流業界におけるエネルギー消費量の増加、環境負荷の増大といった課題があります。
政府は、これらの課題を解決するために、荷主にも省エネ化を推進する責任を負わせることで、物流業界全体の省エネ化を加速させようとしています。
特定荷主制度は、持続可能な社会の実現に向けて、物流業界が取り組むべき重要な課題の一つと言えるでしょう。
特定荷主の義務と規制
特定荷主には、省エネ法によって以下の3つの義務が課せられています。
中長期計画の作成
3年以上の中長期的な視点で、省エネの目標や具体的な取り組みをまとめた計画書を作成し、経済産業大臣に提出する義務です。計画には、エネルギー使用量の削減目標、輸送効率の向上に向けた施策、モーダルシフトの推進など、具体的な内容を記載する必要があります。
計画書の作成にあたっては、以下のポイントを意識しましょう。
- 現状におけるエネルギー使用量の把握
- 具体的な削減目標の設定
- 実行可能な省エネ対策の検討
- 定期的な進捗状況の確認
- 計画の見直し
計画書は、特定荷主の省エネへの取り組み姿勢を示す重要な資料となります。
定期報告
毎年度、省エネの取り組み状況や実績をまとめた報告書を経済産業大臣に提出する義務です。報告書には、エネルギー使用量、貨物輸送量、CO2排出量などのデータに加え、計画に対する進捗状況や課題などを記載する必要があります。
報告書の作成にあたっては、以下のポイントを意識しましょう。
- 正確なデータの収集
- 分かりやすいデータの提示
- 計画との整合性
- 課題や改善点の明確化
- 今後の取り組み方針
定期報告を通じて、PDCAサイクルを回し、継続的な改善を図ることが重要です。
貨物輸送量届出書
前年度の貨物輸送量が基準を超えた場合、経済産業大臣に届け出る義務です。
これらの義務を怠ると、罰金が科せられる可能性があります。
さらに、2024年の法改正により、特定荷主はCLO(Chief Logistics Officer:物流統括管理者)を設置することが義務付けられました。
CLOは、企業全体の物流を統括し、省エネ化を推進する責任者です。 CLOの設置により、より効率的・効果的な省エネ対策の実施が期待されます。
特定荷主ガイドライン
特定荷主の義務をスムーズに履行し、効果的な省エネ対策を推進するために、「特定荷主ガイドライン」が公表されています。
ガイドラインには、荷主と物流事業者間の連携強化、情報共有、共同での省エネ活動など、具体的な事例やノウハウが紹介されています。
その他、ガイドラインには以下のような内容が記載されています。
- 荷主と事業者間における運賃・料金設定に関する問題
- 荷主による不公正な取引方法
- 3PL(サード・パーティ・ロジスティクス)事業者への委託
- 荷主が取り組むべき省エネ対策
- 業務効率化、輸送効率化に向けた取り組み
- 環境負荷の低い輸送モードへの転換
- モーダルシフトの推進
- トラック輸送の効率化
- 倉庫保管の効率化
- 輸送ルートの見直し
- 積載率の向上
- エコドライブの導入
- 車両の軽量化
- 燃料転換
- ITシステムの活用による輸送管理の効率化
- 省エネ法に関するよくある質問
- 相談窓口
- 支援制度
- 関係法令
- 参考資料
よくある質問
Q1. 特定荷主に該当するかどうか、どのように判断すればよいですか?
A. 前年度の貨物輸送量を計算し、基準値を超えているかどうかを確認します。貨物輸送量は、輸送トン数に輸送距離(キロ)を乗じた「トンキロ」で算出します。
具体的には、以下のいずれかの条件を満たす場合、特定荷主に該当します。
- 貨物輸送量が 3,000万トンキロ以上
- トラック輸送で 9万トン以上 の貨物を取り扱う
ご自身の会社が特定荷主に該当するかどうかは、以下の方法で確認できます。
- 貨物輸送量の計算: 過去の出荷データなどを基に、貨物輸送量を算出します。
- 省エネ法の告示: 省エネ法の告示に記載されている特定荷主の一覧を確認します。
- 経済産業省への問い合わせ: 経済産業省または管轄の経済産業局に問い合わせます。
Q2. 中長期計画や定期報告の作成が難しいのですが…
A. 中長期計画や定期報告の作成には、専門的な知識や経験が必要となる場合があります。もし、作成が難しい場合は、以下の方法を検討してみましょう。
- 省エネ診断: 専門家による省エネ診断を受けることで、自社の課題や改善点、具体的な省エネ対策を把握することができます。
- コンサルティングサービス: 省エネの専門家によるコンサルティングサービスを利用することで、計画作成から実行、報告まで、一貫したサポートを受けることができます。
- 支援ツール: 経済産業省などが提供する支援ツールを活用することで、計画書や報告書の作成を効率的に進めることができます。
- 参考資料: 省エネ法のガイドラインや事例集などを参考に、計画書や報告書を作成することができます。
Q3. 特定荷主の義務を怠ると、どうなるのでしょうか?
A. 特定荷主が省エネ法で定められた義務を怠った場合、以下の措置がとられる可能性があります。
- 勧告: 経済産業大臣から、改善に向けた勧告を受けることがあります。
- 命令: 勧告に従わず、改善が見られない場合は、経済産業大臣から、必要な措置をとるよう命令を受けることがあります。
- 罰金: 命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられることがあります。
特定荷主の皆様は、法令を遵守し、積極的に省エネに取り組むことが重要です。
Q4. 荷主と物流事業者は、どのように連携すればよいのでしょうか?
A. 荷主と物流事業者は、以下のポイントを踏まえ、積極的に連携することが重要です。
- 情報共有: 互いに、物流に関する情報(貨物量、輸送ルート、配送時間など)を共有することで、輸送効率の向上や環境負荷の低減につながります。
- 共同での省エネ活動: 共同で省エネ活動に取り組むことで、より効果的な省エネ対策を推進することができます。
- 相互理解: お互いの立場や課題を理解し、協力体制を築くことが重要です。
Q5. 省エネ化を進める上で、どのような課題がありますか?
A. 省エネ化を進める上で、以下のような課題が挙げられます。
- コスト: 省エネ設備の導入や輸送ルートの見直しなど、コスト面での課題
- ノウハウ: 省エネに関する知識やノウハウ不足
- 意識: 社内における省エネ意識の低さ
- 人材: 省エネ推進を担う人材不足
これらの課題を克服するためには、政府の支援制度の活用、社内教育の実施、外部専門家との連携などが有効です。
まとめ
特定荷主制度は、物流業界全体の省エネ化を推進するための重要な制度です。特定荷主の皆様は、省エネ法の規定を理解し、積極的に省エネ対策に取り組むことが求められます。
本コラムで解説した内容を参考に、自社の物流における省エネ化を推進し、持続可能な社会の実現に貢献していきましょう。
より詳細な情報や具体的な事例を知りたい方は
こちらをダウンロード!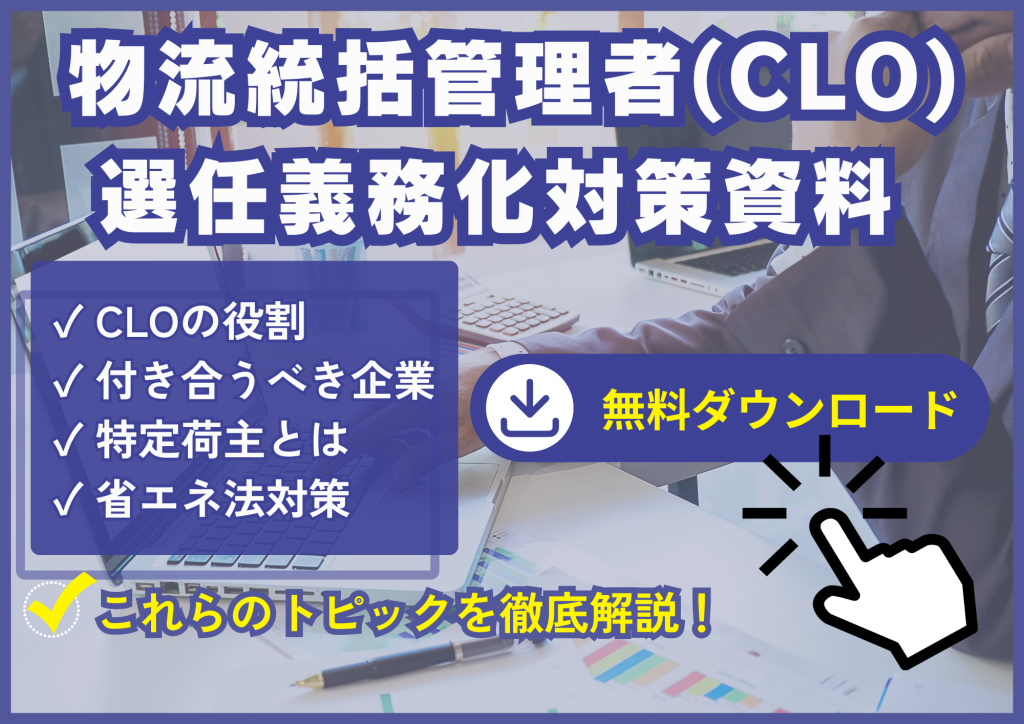
- 経済産業省 資源エネルギー庁:https://www.enecho.meti.go.jp/
- 国土交通省:https://www.mlit.go.jp/
会社概要
社名:株式会社ナカノ商会
本社所在地 〒134-0083
東京都江戸川区中葛西3丁目18番5号
TEL:03-5667-8877(代表)
FAX:03-3531-8321
創立:昭和63年8月(1988年)
